ぼんやりとした不安の近代日本|浜崎洋介|読書会感想
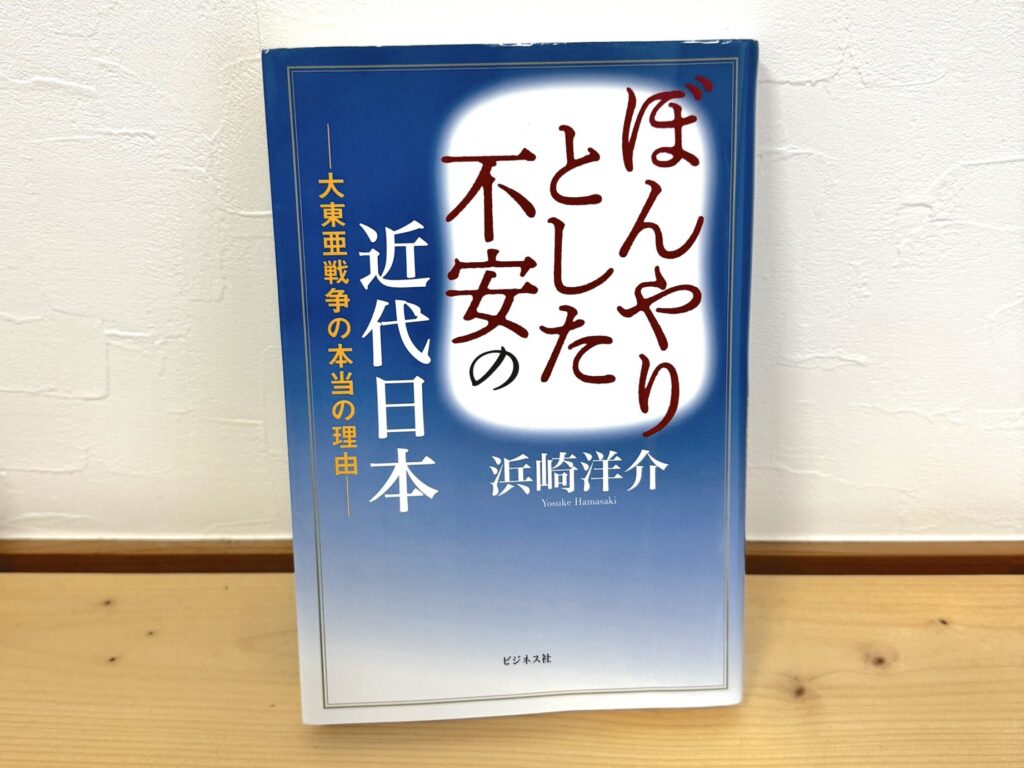
この本は、「日本人はなぜ近代化の中で自分を見失っていったのか?」というテーマで、明治から戦後までの流れを通して考えた一冊だった。
明治維新から西洋化が急速に進む一方で、日本人の心や生活感覚がその変化に追いつかず、内側と外側のズレが大きな不安を生んだ、その不安は社会全体へも影響して、さまざまな要因と重なりながら、戦争へ向かう時代の流れの一部をつくった、そんな見方が本書にはあった。
近代日本で起きたこと
明治維新から日本は西洋の文化・制度を一気に取り入れ、先進国に並ぶための改革を続けた。
それは国を守るためにも必要な選択だったが、スピードがあまりにも早かったため、人々の生活感覚は変化に追いつけなかった。
たとえば漱石の小説三四郎に出てくる「日本は滅びるよ」という言葉や、芥川龍之介の不安と自死など、当時の文学者や文学作品にはこの“不安の影”が色濃く出ている。
漱石や芥川が感じた不安や“自己喪失”は、彼ら個人の問題というより、社会全体が抱え始めていた違和感の兆候だった。
見た目は近代的になっても、内側では「自分は何者なのか」「昔の生活とどこでつながっているのか」 という迷いが大きくなっていった。
自分の中にあった“幹となる価値観”がどこにあるのか分からなくなり、いざ戻ろうとしても、その場所さえも曖昧になっていく——そんな不安が広がっていったのだと思う。
さらに日本は、日清・日露戦争で大きな勝利を収め、近代化の成果を上げていく。しかしその“表面上の成功”が、内側にあったズレを見えにくくし、「この道で間違っていない」という過度な自身につながったと思う。
著者は、日本が大東亜戦争(太平洋戦争)へ向かった背景にも、こうした内側の迷いと外側の期待が入り混じった“複雑な心の動き”があったと読む。
そして、近代化の中で生まれたこの「自己喪失」は、恥ではなく、“初めて大きな他者(世界)と出会ったときの痛み”だったと著者は捉えている。
日本はその痛みを抱えながらも前へ進むしかなかったし、私たちもまた、その歴史の延長線上に立っている。
心に残った部分と、自分へのつながり
特に心に残ったのは、漱石の引用部分「西洋文化は借り物の服みたいなものだ。見た目は立派でも安心できない」(意訳:私の個人主義 大正4年 夏目漱石) という言葉だった。
西洋化によって私たちの暮らしは便利になったけれど、その一方で、日本人が昔から持っていた生活感覚や歴史観とはスムーズにつながらない部分があった。
その“つながらなさ”こそ、本書が言う「所在のなさ」の正体だと感じた。
過去とのつながりが感じられないと、自分の立ち位置が見えにくくなる。 ただ新しい文化を受け入れるだけでは根が育たない——その感覚は、私自身にもよく分かる。
私はアートや文化、日本の歴史に関心があるが、その背景には “自分の生活や価値観が、どんな積み重ねの中から生まれたものなのか” を知りたいという気持ちがあるのだと新ためて気がついた。
西洋化が悪いという話ではなく、 私たち自身が「過去と現在のつながり」を意識しないまま生きると、内側の感覚が置き去りになる。 だからこそ、歴史を学び、自分が立つ場所を知ることが大切なのだと思えた。
まとめ
近代日本が経験した「過去との断絶」「自己喪失」は、単純な失敗ではなく、 世界という他者と出会ったことで生まれた“成長の痛み”だったのかもしれない。
大切なのは、過去を美化することでも、否定することでもなく、そのまま受け止めて自分とのつながりを考えること。
そうすることで初めて、次の一歩が見えてくる。本書はそんな姿勢を教えてくれる一冊だった。

