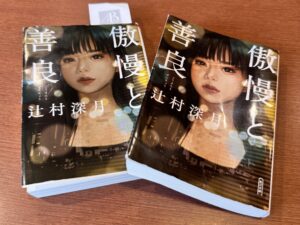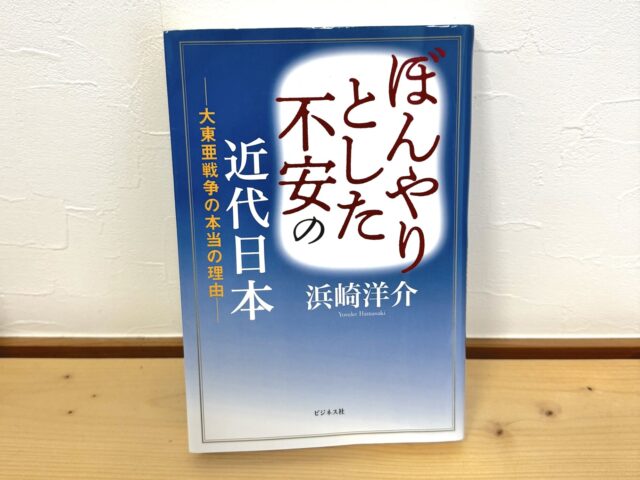暗殺|柴田哲孝|読書会感想
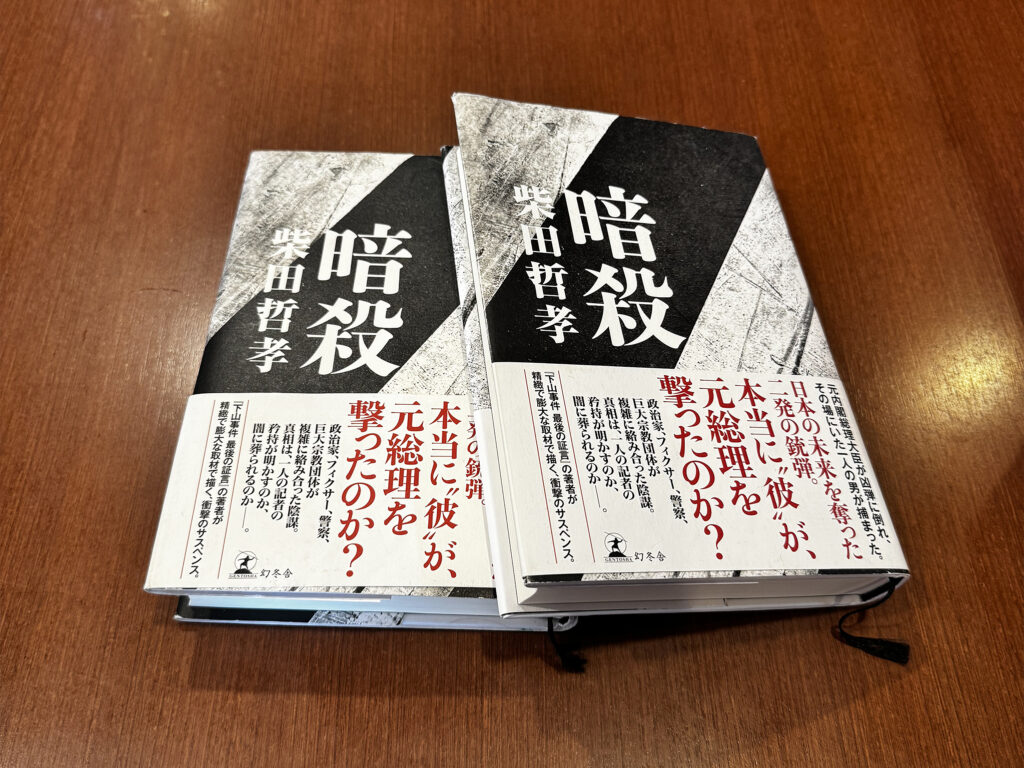
以前勤めていた会社でのこと。
休憩中の喫煙室で、同僚のAが声を潜めて言った。
「どうやら工場長が、会社の実権を握るために営業部長の失脚を画策しているらしい。」
普段から折り合いの悪い二人であることは、社内でも周知の事実だったが、まさかそこまでの話になるとは――。
「本当に工場長がそんなことを?」
「でも、ついに決裂の時が来たのかもしれない…」
まるで推理小説の登場人物になったような気分で、私たちはその“真相”を推し量ろうとした。けれど、噂話に明確な答えなどあるはずもない。
捉え所のない「真実」は、吐き出された青白い煙のようにモワモワと漂い、やがて世間と折り合いを付けるように、上空に消えていった。
その後、工場長は会社を去り、営業部長は専務取締役に昇進した。
だが、役員の間で何があったのか、私のような一平社員には知る由もない。
新しい体制のもとで会社の方針は少しずつ刷新されていったが、私たち愛煙家は変わりゆく日常を尻目に、相変わらず喫煙室で紙タバコを燻らせていた。
――そんな出来事を、柴田哲孝の小説『暗殺』を読んでいてふと思い出した。
本書は、2022年に起こった安倍晋三元首相の銃撃事件をモチーフにしたフィクションだ。
物語は「単独犯」とされる容疑者に疑問を持つ雑誌記者の視点で進む。
容疑者は、政治的動機として被害者と宗教団体との関係を訴えるが、記者の目にはどこか引っかかるものがあった。
やがて、致命傷となった銃弾の角度や、別方向から撃たれた可能性など、現場には不可解な点が浮かび上がってくる。
その裏で政治家・警察・宗教・民族派右翼などいくつもの思惑が絡まり、蠢く姿が描かれる。
記者が追う「真実」は、断片と憶測の上に成り立っており、最後まで核心には届かない。
それでも、何かに近づいていく感覚が行間の奥にあった。
頁を捲るたび、心の天秤は「真実」と「陰謀論」の間を絶え間なく動き続け、最後まで読み応えのある内容だった。
実際に起こった、しかも歴史的転換点とも言える事件を題材とした小説だけに、本を閉じて尚、考えさせられることは大きい。
決して一つではない正義や膨大な利権、それぞれが思い描く多様な理想。その微妙な均衡と軋轢の間で世界が成り立っていること。
そして小さな会社の瑣末な権力闘争すら真実を知らない平社員に、本書の投げかける問題定義は途方もなく巨大で、何かを掴み取るのに、その手はあまりにも短かすぎる。
それでも、あの喫煙室で交わされた「…らしい」という噂話は、真理を追いかける感覚にどこか似ていた気がする。
誰も辿り着けない“何か”に触れようとしていたような――そんな奇妙な高揚感。
複雑な世界で自分達だけが”何か”を知りうることの優越感。
だが、そこには「…だった」という事実は一つもない。
噂の熱が冷めたあとには、陰謀論に躍らせれた自分だけが取り残されたような、漠然とした虚無感が広がっていた。
あの喫煙室は、この国の縮図であったのかも知れない。
そしてきっとこれからも、真実が埋まったアスファルトの上で、私たちはただ煙を燻らせ続けるしかない――
そんなことに気づかされる一冊だった。